- ホーム
- 江戸紫と京紫
江戸紫と京紫
2020/11/19江戸紫と京紫
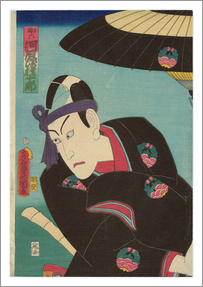
古代より、洋の東西を問わず、
あこがれの色とされてきた紫ですが、
特に、江戸時代においては
様々な工夫をして、
一般庶民にも手が届くものも出てきました。
というのは、
紫根染めによる紫が禁制となったので、
茜や蘇芳を使って
色を作り出すことを工夫しはじめたのです。
紫根染めの紫を「本紫」
茜や蘇芳を使って染めたものを
「似紫(にせむらさき)」と呼んで、
その違いをしっかりアピール。
贅沢を禁止したい幕府と、
したたかにその禁制を
かいくぐって生きていく庶民との、
痛快なバトルが繰り広げられたのでした。
江戸っ子ご自慢の青みを帯びた紫は、
江戸紫と呼ばれ大流行しました。
これは、伝統の京紫(きょうむらさき)に対抗して
つけられた色名のようですが、
実は、
京都上京の染師、石川屋の作
だったとのこと。
赤みを帯びた京紫=古代紫に対し、
江戸紫は今紫(いまむらさき)として、
流行の最先端であることを
アピールしたのでしょうね。
江戸紫は、
歌舞伎「助六」で
主人公が頭に巻いたハチマキの色
としても有名です。





